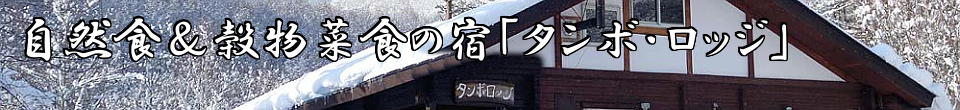足尾在来種の「舟石芋」を使ったチューニョ作りワークショップ開催
2025年の2月の最終日(28日)に、「ナチュラルフード 森の扉」さん主催のワークショップ「インカ文明を支えた100年先へ繋げる保存食 舟石芋のチューニョ作りWS」の講師として呼ばれ、行ってきました。
「舟石芋」というのは、他の地域に出回ることなく、日光市足尾地区にひっそりと残されていた在来種のじゃがいもです。
他の産地のじゃがいもを寄せ付けないほど美味しいじゃがいもですですが、小ぶりなものが多いのが難点だそうですが、その小ぶりなところを利用して、アンデスの究極の保存食の「チューニョ」に加工し、絶滅を防ぐために加工品として是非製品化したい・・・という森の扉の野原さんの熱意に押されて、わたくしも少しながらも協力しようと考えて、実現したワークショップです。
画像はクリックすると拡大します
 当日は午前9時45分に「わたらせ渓谷鉄道」の足尾駅集合です。
当日は午前9時45分に「わたらせ渓谷鉄道」の足尾駅集合です。
 参加者全員が集まったところで、主催者の森の扉の野原さんの挨拶が始まりました。
参加者全員が集まったところで、主催者の森の扉の野原さんの挨拶が始まりました。
 ここから近い、「舟石芋」の故郷の「舟石峠」の場所の説明です。
ここから近い、「舟石芋」の故郷の「舟石峠」の場所の説明です。
この日は車でその峠まで行く予定でしたが、何しろ少し前の降雪により、道路が凍結して危険なことからそれは残念ながら断念しました。😭
 舟石峠に近いふもとまで移動し、近代化の遺産、足尾の山を「煙害」で枯らしてしまった銅の精錬所の煙突が見える場所までやって来ました。
舟石峠に近いふもとまで移動し、近代化の遺産、足尾の山を「煙害」で枯らしてしまった銅の精錬所の煙突が見える場所までやって来ました。
周りの山々は、いまだに枯れていて、大きな木は一本も生えていません。
 山に木がないために、水害も多発。それを防ぐために、立派な砂防ダムがいくつもありました。
山に木がないために、水害も多発。それを防ぐために、立派な砂防ダムがいくつもありました。
水は綺麗で美しく、なんだかびっくりです。😱
 この舟石峠の近くで、足尾の近代化の歴史を振り返るところからスタートしましょうね。
この舟石峠の近くで、足尾の近代化の歴史を振り返るところからスタートしましょうね。
 その後、足尾の公民館に移動して、いよいよアンデスのじゃがいもの究極の保存食「チューニョ」作りのワークショップが始まります。
その後、足尾の公民館に移動して、いよいよアンデスのじゃがいもの究極の保存食「チューニョ」作りのワークショップが始まります。
この「白」と「黒」のチューニョ、同じ舟石芋から先シーズンわたくしが作っておいたものです。
加工方法により、2種類のチューニョに作り分けることができるんです。✊
 小さめの舟石芋を、冷凍庫にて「凍結」と「解凍」を3回ほど繰り返した、チューニョに加工する前の物を、野原さんに事前に準備していただきました。
小さめの舟石芋を、冷凍庫にて「凍結」と「解凍」を3回ほど繰り返した、チューニョに加工する前の物を、野原さんに事前に準備していただきました。
参加者一人当たり1Kgあるそうです。
こんなに沢山の量を準備していただけるとは😲びっくりです。
 さて、アンデス原産のじゃがいもの誕生から、この「凍結脱水乾燥」させて「チューニョ」を作る工程までのざっとした話を私からさせていただき、さっそく加工の実習に移ります。
さて、アンデス原産のじゃがいもの誕生から、この「凍結脱水乾燥」させて「チューニョ」を作る工程までのざっとした話を私からさせていただき、さっそく加工の実習に移ります。
 まずこちらは、圧力をかけてじゃが芋から水分を押し出し、皮を剥いて天日で乾燥させる「黒」を作るやり方です。
まずこちらは、圧力をかけてじゃが芋から水分を押し出し、皮を剥いて天日で乾燥させる「黒」を作るやり方です。
じゃが芋からまるで水鉄砲の様に水分が出てくることにびっくりの参加者たち。😱
 白い方の加工は、水晒ししないといけないので、それぞれ参加者が持ち帰り、お家でやっていただくことになりました。
白い方の加工は、水晒ししないといけないので、それぞれ参加者が持ち帰り、お家でやっていただくことになりました。
そして時間はお昼を少し回ってしまい、お腹もすいてきましたね。🤣
今回は私が事前に用意した、白と黒の2種類のチューニョを使った料理を試食していただきました。
ミートボールのようなものが「黒」から作ったもの、お皿の右の炒り卵をまぶしたように見える方は「白」から作ったスクランブルです。(卵不使用)
 さて、試食した皆様、おいしいですか?。
さて、試食した皆様、おいしいですか?。
少しでもチューニョに関心を持つ方が増え、貴重な絶滅寸前の在来種が守られることを切に願っています。
楽しいワークショップを企画してくださった森の扉の「野原さんご夫妻」、今日はありがとうございます。
これを是非次につなげていきたいですね。🤗